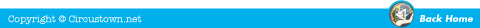| 2014.04.14 - 追悼大瀧詠一 | ||

|
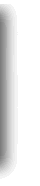
|
君は天然色(後編)
大滝詠一 A Long Vacation (1981) |
 | ||
前編より。
前回では奇跡のサウンド「天然色」の謎を主にエンジニアリングの観点から追った。今回はアレンジとサウンドプロデュースの観点から追ってみたい。
ロンバケで大滝詠一はどのようにアレンジをし、どのように演奏をさせていたのか。正直、現場監督としての大滝詠一の姿が一番想像しにくい。私にとって大滝詠一は第一には《研究家》である。研究家はありとあらゆる可能性を考えることが仕事であるため、現場が弱い。とても一発では決まらない。であるから大滝詠一の現場は、それこそ Steely Dan か 、Brian Wilson か、艱難辛苦の海と想像していたのである(もちろんどっちの現場も知らないのだけど)。ところが「天然色」の録音はワンテイクであったという。
本番ではテイク1でOKでした。ロンバケはさぞやたくさんテイクを費やしていると思われそうなのですが、どの曲もテイク1か2くらいですよ。(大滝詠一・サンレコ 2011年5月号)
「天然色」は一発で決まった。《勝負師》である。どうやったのだろう。「千本ノック」と称される綿密な練習をしたそうであるが、その鍵が雑談に始まる説明会だそうである。
まずは挨拶ですね。いやホントに(笑い)。これは儀式なんですヨ。で、進行の仕方としては、部隊ごとに説明会を行うんです。たいていはまずギターのところに行って「最近どうよ」みたいなところから入って、曲の説明ですね。僕の場合はヘッドアレンジなので、譜面は簡単な構成やキメなんかが書かれてるくらい。なので、口三味線を使いながら「ここで、こんな感じ」って説明する。次にパーカッションのところに行って、また挨拶から(笑い)。(大滝詠一・サンレコ 2011年5月号)
アコギ→パーカス→鍵盤→エレキギター→ベース→最後にドラムと説明会が続く。説明会は1時間以上続くという。次の発言は大滝詠一にしては、はぐらかさずに語っていて貴重である。
各パートの確認がそれぞれできたら、パート同士を会わせてどうなるかをチェックします。ここが一つの山場になります。ミュージシャン側からは「ここはどうするの?」みたいな質問も出てくるし、合わせてみたら頭の中のイメージと違っていることもある。それがミュージシャン側の問題なのか、エンジニア側なのかなど即座に判断する必要があるのでボンヤリしていられないんですね。(大滝詠一・サンレコ 2011年5月号)
まずビジョンを大滝詠一流に伝え、続いて曖昧な点をその場でザクザクと決めていく。実は極めて優れた現場監督である。
その現場は、ロンバケにキーボードとして参加した《右腕》井上鑑の発言で、より見えてくる。
ざっくり言うと、各楽器ごとに解説→部隊ごとの練習→全体練習→本番といった流れでした。大滝さんはヘッドアレンジで簡単なコードと構成だけを決めて進行していく、と伝聞されているようですけど、僕にしたら少し違います。
「鑑、こうしたい」
「それはこんなの?(弾いてみせる)」
「違うなあ」
「ああ、こっちかな?」
「当たり!」
みたいな(笑い)。それをみんなに伝えるリーダーみたいなのが各パートにいると思えば理解しやすい。(井上鑑・サンレコ 2014年4月号)
そしてドラム。とりわけドラムスは大滝詠一の頭の中で完成していた。《心臓》上原裕との関係は無二。
説明会をしながら各パートを回って、一番最後にドラムに行きますよね。これがスゴイのです。僕ら鍵盤のときは大滝さんと多少アイディアの行き来があったりするのだけど、ドラムは全然違う。特にユカリ(上原裕)のときなんてびっくりですよ。頭から最後まで全部決まっているんです。構成とかも最初から全部大滝さんの頭の中にあったということになりますよね。もしかしたら構成とメロディとドラムだけ頭の中で鳴っていたのかもしれません。(井上鑑・サンレコ 2014年4月号)
井上鑑の別のソースからの発言。
ドラムのフレーズなどは口伝で指示され、よく叩けるねーというような、ちょっと聞くと懐かしめ、でも実際演奏するには非常に難しいパターンが頻出する。(中略)細かいニュアンスを指示しながらベーシックの録音が進んでいった。その結果、リズムセクションだけでも完全に成立する音楽が生み出され、無いのはメロディーラインのみといっても良い状態が出来上がった訳である。思い起こせば、演奏上の注文をほとんど受けずに文字通り野放しで弾いていたのは鈴木茂氏一人だけだったかもしれない。茂さんに向かってあれこれ言っても無駄!?という面があるのも確かだけれども、それ以前に全幅の信頼が厳然と感じられた。(井上鑑 Remembering Songbook・NIAGARA SONG BOOK 30th Edition特設ページ Sony Music 2013年3月)
大滝詠一の頭の中にあるサウンドを、スタジオに集まった20余名の当代気鋭のミュージシャンの力を借りて一気に作り上げ、スタジオを知りつくしたエンジニアの力を借りて一気に録りきる。このダイナミズムが「天然色」の瑞々しく力強い楽曲を構成している。私にはドラムスが少し走っているように聴こえる。大合奏のライブレコーディングならではのことだと思う。ドラムスが引っ張るサウンドが好きだ。さらに「天然色」は大滝オーケストラ20名全員で、2回のオーバーダブを行った。「スッタターン♪スッタターン♪」だ。ロンバケ30周年盤の Disc 2 におさめられた「Original Basic Track」と「純カラ」を聴き比べるとわかるだろう。ゴージャス。
しかし、この「音」が鳴る確証がどのように大滝詠一にあったのだろうか。福生時代は基本4リズム録音である。「レコーディング自体は福生時代とあまり変わらず、ダビングを重ねたものをいっぺんにやっただけ」と井上鑑はいうが、なんたる奇跡。コンピューターを100台動かしてもクラウドにはならない。多羅尾伴内楽團の「雪やコンコン」とロンバケの間に何があったのだろう。あったのは数作のCMと須藤薫の「あなただけI LOVE YOU」だけ。これが事実である。どうやって20人オーケストラを確信したのか?どうやってこの壮大なプロジェクトのサポートを取り付けたのか?朝妻一郎さんや当時のCBSソニーの方々に聞けるものならききたいものである。しかしそれだけの勢いが、当時の大滝詠一の周辺に、CBSソニーに、ニューミュージック界に、80年代にあったのである。コロンビア時代を知らないからこそ気楽にいえることだが(笑い)。
最後に。ここまで、かんじんの大滝詠一の《声》と《うた》について一言も書いていなかった。歌い手大滝詠一。Carole King と大滝詠一。松本隆と大滝詠一。《芸術家》大滝詠一。さてさて。
とかく大瀧サウンドはアメリカンポップスのエッセンスを名編集で切り貼りして、という語られ方をするが、現場を知るものから見れば大分ベクトルの逸れた説明でしかない。背景にある文化的知識の量や体験に根ざす感覚、という点では当たっているのだが、大瀧さんの紡ぐメロディーの流れは他の人からは出てこない微妙なバランス感覚の上に成立しており、早い話が日本語の歌としての名作なのである。バックのリズムやコード進行が何かに似ていようがいまいが、実は大した問題ではない。(井上鑑 Remembering Songbook・NIAGARA SONG BOOK 30th Edition特設ページ Sony Music 2013年3月)
いろいろ書きましたが、実はここからが本当の「天然色」の謎の始まりのようであります。
(追記)
ロンバケのデジタルリマスターに関しては、かなり詳細な証言が残されている。これもロンバケと「天然色」の奇跡を語る上で欠かすことができない。20周年盤と30周年盤にかかわったソニーミュージックのエンジニア柿崎景二氏著の「デジタルーディオの全知識」(白夜書房)には大滝詠一との対談が38ページも掲載されている。この本(教科書)自体すごく面白い。
(たかはしかつみ)
シェアする