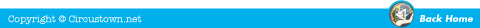| 2014.07.30 - 追悼大瀧詠一 | ||

|
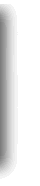
|
Do I Have To Come Right Out
Buffalo Springfield Buffalo Springfield (1966) |
 | ||
先月はJack Nitzscheを取り上げたが、その時Buffalo Springfieldのことに触れたので今月はその流れで彼ら、Buffalo Springfieldのことについて取り上げてみたいと思う。
Buffalo Springfieldは1966年に結成され3枚のアルバムを残して、活動期間わずか2年ほどで68年に解散している。バンドとしての活動期間は短かったが、その後のメンバーの活動も含め、様々なミュージシャンたちに大きな影響を与えたバンドとして知られている。
メンバーは、Neil Young(G,Vo)、Steve Stills(G,Vo)、Richie Furay(G,Vo)、Bruce Palmer(B)、Dewey Martin(Ds)、のちにBruce Palmerに代わりJim Messina(B)が加わる。それぞれがアメリカン・ロック界の大物ばかり。
Steve StillsはBuffalo解散後、Al Kooperの”Super Session”に参加したのち、Neil YoungとともにThe ByrdsのメンバーだったDavid Crosby、元The HolliesのGraham NashとCrosby, Stills, Nash & Young(CSN&Y)を結成する。
Richie Furayはあとから参加したJim MessinaとともにPocoを結成。PocoにはのちにEaglesに参加することになる、Randy MeisnerやTimothy B.Schmitも名前を連ねている。
さらにJim MessinaはPocoを経てKenny LogginsとLoggins and Messinaとして活動していた時期もある。
Neil Youngは自身のソロとしての活動でも独特の存在感を放っていることは広く知られており、こうして人脈を辿っていくだけでもBuffaloが後のウエストコーストを中心とするロックに大きな影響を与えていることがよく分かる。
そして日本のはっぴいえんどもBuffaloから多大な影響を受けたバンドの一つである。はっぴいえんどにBuffaloというコンセプトを持ち込んだのは細野晴臣で、はっぴいえんどの前身、エイプリル・フールで一緒に活動していた松本隆、小坂忠とBuffaloのようなバンドを作ろうという構想で一致していたようで、これがはっぴいえんどへとつながっていく。
一方、当時大瀧詠一は、布谷文夫と行動をともにしながら布谷が活動していたブルース・クリエーションのステージに飛び入してElvisの真似をしてみたり、作曲家中田喜直の甥、中田佳彦と組んでEverly Brothersのコピーをやったりしていたが、ポップス好きの少年が東京に出てきて漂っているような感じだったという。
そのブルース・クリエーションには竹田和夫もいて、当時大瀧は仕送りをレコードにつぎ込んで食えなくなると竹田の家に出かけて行って飯を食わしてもらったり、コーラの壜を売って電車賃を稼いでやっとの思いで布谷の家に辿り着くというようなことをしていたのだそうだ。
話がそれてしまったがその竹田とたまたま聴いたのがBuffaloの「For What It’s Worth」のシングル盤だった。大瀧はあまり興味がなくてまじめに聴いていなかったのだが、竹田がこっちのほうが好きだと言ってかけたのがB面の「Do I Have To Come Right Out」で、これが大瀧の慧眼を開いた。この曲のほうがむしろA面の「For What〜」よりもいい曲だなと思う。そう思って「For What〜」を聴き直してみてその良さにも気が付く。
中田を通して知り合いになっていた細野にその話をすると、じゃあ一緒にやろうということになる。この時大瀧は細野がBuffaloのようなバンドを作りたいという構想を抱いていることを知らなかったというのだから、偶然がまさに天の配剤となったのだ。
はっぴいえんどが誕生する。
Buffaloの残した3枚のアルバムははっぴいえんどの3枚に何となく呼応してはいないか。
大瀧が惹かれたという「Do I Have To〜」は「For What〜」とともに彼らのファースト・アルバム『Buffalo Springfield』に収められている。LAで起こった暴動事件を題材にした「For What〜」がヒットしたこともあって、それなりに注目されたアルバムであった。66年という時代はフォーク・ロック、スワンプ・ロックやカントリー・ロックのようにロックの道筋が細分化し始め、ロックを取り巻く状況が大きなうねりを伴っていた時期である。メンバーそれぞれの個性がうまく溶け合ってひとつの色を成しているアルバムだと思う。これは粗さは伴うもののそれぞれの個性が際立つ『ゆでめん』に。
続く2枚目の『Again』は高密度でさらに高い位置でメンバーが調和している。とりわけ「Bluebird」の緊張感の高いギターは傑作であり、はっぴいえんどもこの曲を好んでステージで演奏していた。『Again』はやはり傑作との評価が高い『風街ろまん』ではないか。
Neil YoungとSteve Stillsの確執やメンバーの度重なる不祥事で解散が決まっていた3枚目の『Last Time Around』はNeil Young、Steve Stillsの陰に隠れていたRichie Furayが才能を発揮しており、同じく解散が決まって出された3枚目で鈴木茂が躍動した『Happy End』と重なる。
Buffalo Springfieldは時代の転換点に位置して漂いながら、様々な曲折を経ていくつもの萌芽を残していた。
69年。世の中は安保で騒然としていたが、21歳の大瀧はそうした同時代的な社会とは無縁の立場でいた。彼にとっては純粋に音楽とどのように関わっているかということが興味の対象であって、音楽が政治的なものと同時代的に意図的に関わっているということとは常に無縁の立場でいたかったと語っている。
大瀧が幼いころから親しんできたポップスから一歩抜け出してBuffaloに出会ったはっぴいえんど前夜の69年。まだ若き大瀧詠一もまた時代の中で漂いながら、しかし淡々と彼らしく、まさに雌伏の時を過ごしていたのだ。
今日の1曲
Tweet