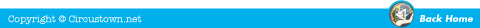| 2014.10.30 - 追悼大瀧詠一 | ||

|
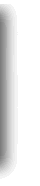
|
Iko Iko
Dr.John Gumbo (1972) |
 | ||
『Niagara Moon』のアルバムの重要なキーワードの一つが“ニューオリンズ”であることは、そのサウンドを聴けば明らかでもあるし、このアルバムが発売された当時の大瀧さん自身の手によるライナーノートにも書かれてあることなのだけれども、何度もこのアルバムを聴きながら長いこと僕はそのことに今ひとつ鈍感だったような気がする。多様なリズムパターンやアメリカン・ポップスへのオマージュ、ノベルティで楽しい歌詞などいくつもの要素が練りこまれたアルバムだから、ベースとなっている“ニューオリンズ”というアイコンに注意が向かなかったのだと思う。何とも粗忽な聴き方をしていたと思う。
ライナーノートを読むとHuey Smith、Ernie K.Doe、Alvin Tyler、Alan Toussaint、Fats Domino、Professor Longhair、The Metersとニューオリンズのアーティストたちがたくさん登場している。
はっぴいえんどの解散と前後して出されたファースト・ソロアルバムの『大瀧詠一』には、はっぴいえんどの残り香と大瀧さんの好きなポップスへのオマージュが微妙なバランスで同居していた。
ナイアガラ・レーベルが立ち上がって、シュガー・ベイブの『SONGS』でメロディー・タイプのアルバムが第1弾としてリリースされたことによって、自身のソロをどういう方向にもっていくかについて大瀧さんはプロデューサー的なバランスを取ったのではないかと思われる。
大瀧さんはシュガーを最初はコーラス・グループとして捉えていた。そしてシュガーのコーラスを起用して「ジーガム」や「Cider’74」を制作する。
大瀧さん本人としてはメロディー・タイプについてはひとまずCMソングで溜飲を下げておいて、ナイアガラでのソロ・アルバムでは思い切りドライに舵を切ったのではないか。日本初のプライヴェート・レーベルへの主宰者としての愛情が覗える。
はっぴいえんどのラスト・アルバムでロサンゼルスに滞在しているときに、大瀧さんはJohnny Riversのライブを観に行く。それからLittle Featの「Dixie Chicken」のレコーディング現場にも立ち会うのだが、ここでニューオリンズに開眼する。“ポストはっぴいえんど”をニューオリンズ・サウンドで展開するというアイデアはこの辺りにきっかけがあるのだと思う。『Niagara Moon』でその志向が一気に展開される。
一方、はっぴいえんどから解き放たれた大瀧さんは幼いころから聴いてきたアメリカン・ポップスやロックンロールのエッセンスをふんだんに散りばめていく。この作業はきっと楽しかったに違いないと思う。
その筆頭はElvis Presleyだ。クレジットのDedicationは「論寒牛男」のElvis。大瀧さんにとってのElvisはまさにアイドルで、とりわけそのヴォーカル・スタイルの影響は随所に垣間見られる。ロックンローラーとしてはシャックリ唱法を捧げた「シャックリママさん」のBuddy Holly、「ロックン・ロール・マーチ」でBill Haleyなどが取り上げられている。
ブリル・ビルディングのソングライターとしてはEydie Gormeの「Blame It On The Bossa Nova」をメレンゲに仕立てた「恋はメレンゲ」のBarry Mann&Cynthia Weil。Neil SedakaやCarole King、「ハンド・クラッピング・ルンバ」にはCharlie Calleloの名前もある。
さて、その「ハンド・クラッピング・ルンバ」である。この曲のコンセプトがShirley Ellisの「The Clapping Song」でそのプロデューサーがくだんのCharlie Callelo。The Metersの「Hand Clapping Song」と合わせてライナーノートにクレジットされている。
さらにこの曲がべーシックなサウンドとして取り入れているのがDr,Johnの「Iko Iko」である。72年にDr.Johnが先祖返り的にニューオリンズのR&Bを取り上げた『Gambo』は日本でもちょっとしたニューオリンズのブームを巻き起こす。Dr.John自らが楽曲解説を行っているところも『Niagara Moon』との共通点を感じさせる。
アルバムの1曲目がこの「Iko Iko」でこれは「ハンド・クラッピング・ルンバ」だが、2曲目の「Blow Wind Blow」は細野さんの「蝶々San」だ。奇しくもはっぴいえんどの二人が同じニューオリンズのR&Bに傾倒していたというのは興味深い。当時のこのアルバムの影響力が伺える。(ちなみに「蝶々San」には大瀧さんが“山下よた郎”とともにコーラスで参加しているというのも何かの符号?)
そしてさらにルンバである。大瀧さんはライナーノートの中で“ニューオリンズのリズムの中には、ルンバのリズムが重要なパートを占めている事も僕が魅せられた原因なんです”と語っている。なんと重層的な!
そして、こうした重層的なサウンドを支えた才能と個性あふれるミュージシャンたちのグルーヴ感あふれる演奏なしにはこのアルバムはなかった。
リズムセクションの核をなしていたのは、林立夫(ds)、細野晴臣(b)、鈴木茂(g)、佐藤博(kbd)。キャラメル・ママとハックル・バックの混成メンバー。キーボードのオーヴァー・ダビングとして松任谷正隆。さらにここにシュガー・ベイブから上原裕(ds)、寺尾次郎(b)、伊藤銀次(g)が加わる。弦のアレンジは若き日の山下達郎が担当。こうしたパーソネルで繰り広げられた圧巻のグルーヴとその表現力は当時メンバーのほとんど20代であったことを考えると驚嘆に値する。
とりわけ、ニューオリンズ・テイストを支えていたのは佐藤博の圧巻のピアノ・プレイだと思う。Professor Longhairを彷彿とさせる雰囲気満点のピアノを披露していて、林立夫のセカンドライン・ドラムとともにアルバムの顔と言っていい。
端的に言えば『Niagara Moon』はニューオリンズのビートをベースに置きながらノベルティー・タイプのポップスをモチーフに据えて、はっぴいえんど時代とは対をなす極端なアプローチが存分に繰り広げられているアルバムだ。
でもその深さと拡がりと、織り込まれた大瀧さんの意図や思いを、このアルバムを初めて聴いてから30年以上を経た今になってもまだ完全には感じきれていない。当方の不徳の致すところではあるけれども、好奇心のツボを刺激されながら、研究や調査や勉強がまだまだ続けられるというのはとっても幸せなことだと思うのだ。
今日の1曲
Tweet