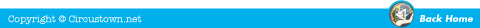| 2014.11.30 - 追悼大瀧詠一 | ||

|
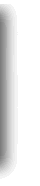
|
Have I The Right
The Honeycombs (1964) |
 | ||
初めて『A Long Vacation』を聴いたときに違和感を覚えたのが、最後の「さらばシベリア鉄道」だった。この曲だけはマイナー調で哀愁があって明らかに雰囲気が違う。なんだかとってつけたような感じ。太田裕美に提供した曲のセルフカヴァーだったということもあるのだろうけど、それまでの流れがこの曲で断ち切られているような感じさえした。
それもそのはずで、アルバムは実は「FUN×4」の“アンコール、アンコール”のフェイドアウトで大団円を迎えるはずだったのだが、あとから「シベリア鉄道」が追加される編成になったらしい。ジャケットから『ロンバケ』は“夏のアルバム”という刷り込みがなされていたことも違和感に繋がったのだろうけど、やっぱりJoe Meekをそれと分かる形で持ってきたことは大きかったのだと思う。最初はアルバムの最後にこの独特の哀愁サウンドを持ってきたのを不思議に感じていた。
「シベリア鉄道」はリズムや全体の構成がJohn Leytonの「Johnny Remember Me(霧の中のジョニー)」を下敷きにしているし、漂う雰囲気やメロディーラインはThe Tornadosの「Ridin’ The Wind」をベースにしており、はっきりとJoe Meekサウンドをオマージュした格好になっている。
私がJoe Meekサウンドを初めて聴いたのはTornadosやJohn LeytonではなくThe Honeycombsの「Have I The Right」だったような気がする。もう30年以上も昔の話だが、ラジオから流れてきたのを聴いたのだと思う。Joe MeekはPhil Spectorに比べれば日本での認知度は圧倒的に低い。最初はJoe Meekのプロデュースした作品だとは知らずに聞いていた。と言うか当時はJoe Meekその人を知らなかったのではないかと思う。
Honeycombsは1964年にこの「Have I The Right」でデビューを果たし、同時にこの曲で全英ナンバー1を獲得している。ビートルズが世界を席捲し始めた頃で、ブリティッシュ・インベイジョン真っ盛り。大瀧さんも最初はそうしたヒット曲の1曲として聴いていたのかもしれない。プロデューサーJoe Meekが「霧の中のジョニー」や「Telstar」と共にもっとも成功した作品でもあり、イギリスのロック史を語るうえで欠かせない曲でもある。「君は天然色」でもHoneycombsの曲をモチーフの一つとして取り上げているが、大瀧さんは数あるブリティッシュ・ビート勢の中でもHoneycombsが好きだったのではないだろうか。
Joe Meekという人はもともとレコーディング・エンジニアから出発した人で、楽器もできず譜面も読めなかったそうだが、独特のエコー処理や、個性的な発想でちょっと不思議な感覚のポップスを次々に生み出していった。エンジニア的な発想のプロデューサーにして個人レーベルのオーナーというところに大瀧さんは特にシンパシーを感じていたのではないだろうか。
大瀧さんがJoe Meekを取り上げたのは『ロンバケ』が初めてというわけではなく、すでにアルバム『多羅尾伴内楽団VOL.1』でJohn Leytonの「霧の中のロンリー・シティー」とTornadosの「Telstar」をカヴァーしている。
ところでその『多羅尾伴内楽団VOL.1』のライナーノートには“哀愁さうんど同好会”なるクレジットがある。この“同好会”のメンバーに大阪で輸入レコード店“Forever”を経営し、同名のオールディーズ専門誌を作っていた故宮下静雄さんと目黒国隆さんの名前がある。大瀧さんは当時宮下さんや目黒さんとの交流を通じてエレキ・インストものをたくさん聴いたと語っている。「Telstar」をThe Venturesがカヴァーしていることからも分かるように、アメリカのエレキ・インストものはヨーロッパ、とりわけ北欧のインスト・バンドへとどういうわけか自然に繋がっていく。エレキ・インストを聴いているうちに“テルスター”に乗ってJoe Meekへと繋がっていったのか・・・。大瀧さんは63年、中3の頃に聴いた「霧の中のジョニー」と「Telstar」が思い出の曲だったとも語っており、ギター・インストものを大量に聴く中で、若い頃に聴いていたJoe Meekを再認識していったのではないか。
大瀧さんの哀愁サウンド・・・、もうひとつのヒントはこの“同好会”に中田喜彦さんの名前があることだ。中田さんは作曲家中田喜直さんの甥にあたり、大瀧さんと細野さんとともにかつてランプポストというユニットで作曲や楽曲研究などをやっていた。私は彼の名前がここにあるのは単にこのアルバムで叔父の中田喜直さんの「雪の降る街を」を取り上げているからだと思っていた。だが、ここに中田さんの名前があるのはそれだけではないような気がする。
ランプポストの頃、中田さんと大瀧さんは一緒に曲を作っていたそうだ。中田さんはメロディアスな曲を作る人で、当時の大瀧さんは中田さんの才能に嫉妬すら感じていたと言う。中田さんはSimon&GarfunkelやAsocciationなどを熱心に聴いていたそうだが、大瀧さんは、ロックンロールの洗礼を受けながらも、叔父の中田喜直さんの童謡で育った郷愁みたいなものを彼の音楽から感じとったと言う。
2人で共作のようなことをやる中で生まれたのが「レイクサイド ストーリー」の元になった曲で、途中のマイナーになる部分は中田さんと作った曲のコード進行をそのまま使ったのだそうだ。大瀧さんは、中田さんの存在が曲を作るという意味合いにおいては非常に大きかった、彼は偉大なソングライターだったと語っている。叔父の中田喜直さんから受け継いだ中田喜彦さんの愁いを含んだ楽曲センスも大瀧さんの哀愁サウンドに大きな影響を与えたのだと思う。
大瀧さんの哀愁サウンドのもう一つの源流はここにあるのではないか。
『多羅尾』には、滝廉太郎の唱歌「雪やこんこん」も収められているので、滝廉太郎−中田喜直−Joe Meek−大瀧詠一のラインが浮かび上がってくる。言い換えればJoe Meekを仲介者として「雪やこんこん」−「雪の降る街を」−「霧の中のジョニー」−「シベリア鉄道」−「レイクサイド」へと系譜は連なる。かなり強引だけど(笑)。
そして、本当に大事なこと。独特の湿感を持った哀愁あるメロディーを取り入れたのは何よりも大瀧さんが北国の出身で、冬の雪原を原風景として持っていたからではないか。大瀧さんの哀愁サウンドへの思いは故郷の岩手の風景と、だからふるさとへの想いと地続きになっていたのだと思うのだ。
今日の1曲
Tweet